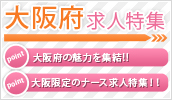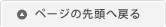第13回 黒岩裕治の頼むぞ!ナース
黒岩祐治の頼むぞ!ナース

第13回 〜社会的入院について思うこと〜
「日本の医療は崩壊する」そんな悲痛な叫びを最近、特に耳にするようになりました。先の国会で医療制度改革関連法が成立したのですが、これがその大きな原因となっています。特に現在38万床ある療養病床を6年間で15万床に削減することが決まりましたが、これにより行き場を失う患者が大量に出てくるのではないかと心配されているのです。

そもそも療養病床削減の方針が打ち出された背景には、医療が必要でないのに入院を続けているいわゆる「社会的入院」が入院患者の半数に及んでいるという現実がありました。こういう患者がいることによって、病院は過重な負担を強いられ、医療費は高騰し、医療の効率化を阻んでいることが問題視されたのです。
厚生労働省の基本的な考えは、限られた医療資源を効率よく使い、医療費の高騰をできるだけ抑えようというものです。そのために、病院のあり方を根本的に洗い直し、大胆な再編を断行しようとしています。
これまでの病院は急性期の一般病床と慢性期の療養病床の二つに分けられていました。そして、それ以外は福祉施設の担当でした。それをこれからは病院はできるだけ急性期だけの施設にしていき、後は福祉施設か、在宅医療でカバーしようというのです。そのためにまずは療養病床を激減させることによって、社会的入院の患者の追い出しに取り掛かろうとしているのです。
医療が必要がないのに入院している患者には病院から出ていってもらうというのは、決して間違った判断ではないでしょう。しかし、「社会的入院」という言葉がよく現していると思いますが、要するにそういう患者の多くは入院を続けざるをえないそれなりの社会的ワケがあるのではないでしょうか。
高齢者の場合、入院して症状が改善し退院が決まったことを家族に伝えても、必ずしも喜ばれないと言います。核家族化が進む中で、普段一緒に生活していない親が退院してきたからといっていったい誰が面倒をみるのか。元気なうちならまだしも、年老いて、しかも病気になって、少しよくなったからと言って自宅に戻されたら、「それは迷惑だ」と家族が感じても、責めることはできないのではないでしょうか。
確かに日本の在院日数は諸外国と比べて格段に長く、欧米では病院にいるはずのない患者がたくさん入院していることは事実です。アメリカではお産でも2泊がせいぜいです。私が住んでいた99年当時は1泊が普通でした。私のアシスタントをしていた女性も出産を終えた翌日にはひいひい言いながら、自宅に戻って行きました。アメリカの病院でかかる費用は莫大ですから、苦しくても退院しようとするのは自然なことでした。
しかし、自宅に戻ってからのサポートシステムがしっかりできあがっているから、それほどたいへんな思いをすることはありません。病院と連携した訪問看護体制がしっかりとしていますし、福祉施設や中間的な施設も充実しています。ですから在宅での不安はそれほど大きくはありません。ここが日本と大きく異なるところです。
厚生労働省の病院再編の基本方針の中で、在宅医療の推進も大きな柱の一つになっています。日本でも訪問看護は介護保険制度ができたこともあり、以前に比べてはるかに整備されてきました。しかし、高齢化の進み具合に追いついて行ってないというのが現状のようです。
在宅医療・看護の究極の姿は自宅での看取りです。自分の住んでいる場所で、家族に見守られながら息を引き取ることは理想的な死と言えるでしょう。今回の診療報酬の改訂の中でも、在宅での看取りには大きな点数がつけられることになりました。これは厚生労働省の在宅医療重視の姿勢を明確にアピールするものと言えるでしょう。
在宅医療が理想的だというのはまさにそのとおりではありますが、日本人の生活環境の現実をしっかりと見つめてみた時、その理想は空論になる危険性をはらんでいます。在宅医療を支えるには、それなりの住環境が必要です。介護ベッドはもちろんのこと、その病人の専用の個室、バリアフリー、介護、医療機器などがそろって初めて、病院に準じる生活環境が確保されます。
 お金持ちで広い住宅に住んでいる人は、少なくともハード面では問題ないでしょう。しかし、団地やアパートに住んでいる一般家庭で、それだけのハードを準備することは容易ではありません。たとえ、ハード面でなんとか体裁を整えることができたとしても、在宅医療を支えるマンパワーは絶対に必要です。核家族化が進む中で、それはどこまで可能でしょうか。
お金持ちで広い住宅に住んでいる人は、少なくともハード面では問題ないでしょう。しかし、団地やアパートに住んでいる一般家庭で、それだけのハードを準備することは容易ではありません。たとえ、ハード面でなんとか体裁を整えることができたとしても、在宅医療を支えるマンパワーは絶対に必要です。核家族化が進む中で、それはどこまで可能でしょうか。
パーキンソン病の年老いた母親が病院から退院したのはいいけれど、娘一人でどうやって看ればいいのか途方に暮れていた友人がいました。訪問看護と言えども時間は限られていますし、勤めから帰ったら一晩中、介護を余儀なくされて、夜も眠れずに共倒れになりそうだとこぼしていました。結局、また具合が悪くなったおかげ(?)で、病院に戻ることができたというのですから、なにをか言わんやです。
ちなみにその友人の母親は、再び退院した後、特別養護老人ホームに入所しましたが、そこに入るまでがまたたいへんだったと言います。施設が限られている中で、長い長い順番待ちを余儀なくされたのです。「このまま在宅で母親を看ていると、自分は母親を絞め殺してしまうかもしれない」などと悲痛な思いで訴えたことが効を奏したのか、なんとか入所にだけはこぎつけたということでした。
それでもそこにいられるのは病状が安定している間だけの話で、また、具合が悪くなったら自動的に病院に送られることになってしまいます。すると、特養はまた一から順番を並びなおさなければならず、同じ苦労を繰り返さざるをえないということになっているのです。
在宅医療や福祉施設の受け皿が十分でないにも関わらず、国は療養病床削減を断行しようとしています。そうするとどうなるか、素人でも分かります。医療難民、介護難民と呼ばれるような状態の患者が大量発生するに違いありません。ベッド数の削減目標が先に決まっていますから、どうやってそれに合わせて患者を追い出すかがポイントになってきます。その基準とされたのが「社会的入院」という概念です。
一人一人の患者が入院し続けなければならないワケにいちいち耳を傾けていては、患者の追い出しなどできるはずもありません。そこで、重症度に応じて医療区分1・2・3に分けて診療報酬の点数に大きな差をつけました。そして必要とされる医療レベルの低い医療区分1の患者に出ていってもらおうとしているのです。医療区分1の患者こそ、医療が必要ないのに入院している患者だというわけです。
目標を達成するために、こうした統一基準で大ナタを振るうことは時として必要なことかもしれません。しかし、相手は生身の患者です。きめ細かく見ていかないととんでもない悲劇を生むこともありえます。
全日本病院会副会長の安藤高朗さんは医療区分1の中に明らかに医療が必要な患者が入ってしまうと言います。たとえば「意識障害がある」「経管栄養を行なっている」「頻会な嘔吐や発熱がある」「全身発疹がある」「インシュリンの皮下注射を行なっている」などです。こういった患者さんが在宅で診られるのか、老健施設などで診られるのか、ナースのみなさんが一番よく分かっておられるのではないでしょうか。
 今、国が進めようとしている病院再編の大きな方向性はマクロな視点から見れば間違っていないと私は思っています。しかし、そのためには同時に進めなければならない施策が山ほどあります。現場の声に基づいたミクロな視点に基づいたきめ細かい対応が必要です。そのために医療の最前線にいるナースの役割は重大です。
今、国が進めようとしている病院再編の大きな方向性はマクロな視点から見れば間違っていないと私は思っています。しかし、そのためには同時に進めなければならない施策が山ほどあります。現場の声に基づいたミクロな視点に基づいたきめ細かい対応が必要です。そのために医療の最前線にいるナースの役割は重大です。
ナースが患者を追い出すことが自分の仕事だと割り切って仕事を進めていくと、病院は冷たい殺伐とした雰囲気に包まれるでしょう。現に私の耳に聞こえてくるナースに対する不満には、すでにそういった現状が進行しているのではないかと思わざるをえない点がたくさんあります。
患者の気持ちを汲み取れないナースにナースの資格はありません。患者の痛みを十分に受け止めながら、国全体のマクロな政策とミクロな視点を融合させ、一人一人の患者の救いをどうやって模索していくか。実に難しい仕事でしょうが、こういう時こそ、看護の真価を発揮するチャンスとも言えるのではないでしょうか。(以上)