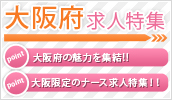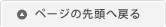第55回 黒岩裕治の頼むぞ!ナース
黒岩祐治の頼むぞ!ナース

第55回 ~特養での看護から看護の真髄を見出す。~
先日、国際医療福祉大学院の博士論文の発表会に立ち会いました。昨年10月に大学院教授に転身した私にとって初めての経験でした。サテライト教室の大田原、小田原、福岡を結んで発表が行なわれ、私は東京・青山の教室にいて、院生のみなさんの力作に耳を傾けました。
特に福祉に関する論文はそのテーマの選び方だけでも発見の連続でした。認知症高齢者の福祉用具のリスクマネジメントや、おむつ・排泄の自立、施設内での肺炎に着目したものなど、たいへん興味深い発表が相次ぎました。
その中で、特に私が関心を抱いたのは、戸塚恵子さんの「特別養護老人ホームで働く看護師が施設看護を見出す過程に関する研究」でした。特養で働く看護師13人に戸塚さんが直接インタビューをし、その内容を分析した実証研究です。

特養で働くようになった動機やきっかけ、特養での看護師の役割ややりがいについて、疑問に思っていることや困難さを感じていることを自由に語ってもらい、録音したものを逐語録し、内容ごとに精査し、分類、分析したものでした。
ナースにとって特養がどういう存在なのかがくっきりと浮かび上がっているような気がしました。勤務した動機が「前向きに希望して」という人はいたものの、「物理的な条件から」「家庭の事情で」「病院より楽かもしれない」「よく知らないままに」など、ほとんどは「前向き」の動機ではありませんでした。
だからこそでしょうか、就職直後にはギャップを感じる人が大半でした。「医師不在で戸惑う看護判断」「病院とは違う看護」「認知症への戸惑い」「介護職への戸惑い」など、ネガティブな言葉が続出しています。
また、ナースたちの抱くジレンマについては、看護判断ができないなど「思うように対応できない」や、病院とは違う「看取りをめぐるジレンマ」、さらに「介護職との関係がうまくいかない」「介護職に十分な教育ができない」など、介護職との連携において大きなジレンマを抱えていました。
また、特養が生活の場であることからくるジレンマも大きいようです。「生活と医療の間に悩む」「病院の医師の理解が得られない」「医療処置に追われる」「入所者と関われない」「家族との関係がうまくいかない」「緊急時の対応が難しい」など、ナースが特養での看護に大きな戸惑いを覚えている実態が浮かび上がってきます。
実にきめ細かく、ナースたちの生の声をすくい取り、分析されている素晴らしい発表でした。しかし、それを聞きながら、私にはナースの世界の抱える大きな問題点を感じていました。確かにナースたちの悩みや戸惑いは理解できる気はしますが、どこか違和感を覚えざるをえませんでした。
それはナースたちは特養など施設での看護について、看護学校や大学でキチンとした教育を受けてきたのだろうかということです。ナースとはそもそも患者に向き合う仕事です。その患者がどこにいようが、関係ないはずです。患者がどんな状況であれ、医療者としてその専門性を活かして向き合うのが看護ではないでしょうか?それなのに、インタビューで浮かび上がった声というのは、施設での看護は想定していなかったかのような内容ばかりでした。
最新の医療機器の整った病院の中で、スタッフはたくさんいて、傍には医師がいて、指示が出され、それを実践し、困った時には看護師長に相談し…という典型的な病院での看護を想定した教育しか行なわれていなかったのではないか?と思わざるをえませんでした。「医師不在で戸惑う」というナースの声を入所者が聞いたら、どれだけ不安に思うでしょうか。医師がいない時こそ、ナースの力の発揮のしどころなのではないでしょうか?
また、介護職との連携に悩むこと自体、入所者としては理解に苦しむでしょう。ジレンマを打ち明けるナースの気持ちの中には、介護職を一段低く見ているようなところがあるような気がしてなりません。「介護職に十分な教育ができない」という声を聞いたら、介護職のみなさんは激怒するかもしれません。そもそもナースは介護職を教育する立場なのでしょうか?
看護と介護のそれぞれの専門性を活かしながら、連携して入所者に向かっていくことがチームとして最も大事なことのはずです。それなのに、介護職を低くみるような意識ではいい連携ができるはずもありません。「介護職との関係がうまくいかない」のは当たり前です。それに加えて、「家族との関係もうまくいかない」というのであれば、ヘタをすれば施設の中で足手まといにもなりかねません。
それはナース自身の問題というより、彼らの受けてきた教育に問題があると私には思えてなりません。戸塚さんも発表の中で「今まで十分な施設看護の教育を受けていない」ことの問題点を指摘し、「(施設看護を)やりながら学ぶ」ジレンマをあげていました。それは実に的確な分析だと思いました。
しかし、戸塚さんの発表はそこで終わっていませんでした。さまざまなジレンマを抱えながらも、ナースたちがそれを乗り越えて成長していく様がイキイキと描かれていました。
就職直後に覚えた戸惑いから経験を重ねていく中で、ナースたちは自分たちの役割を認識していきます。医師が常駐していないために「(医師の)指示を受ける看護から脱出する」ことを目指し始めます。そして、「病院とは違う看護判断」をすることが求められていることに気付き、「多職種と連携する」ことの大切さに目覚め、「介護を支える看護をする」ことこそ、自分たちの役割だと発見するに至るのです。
そうなるとやりがいも感じるようになります。「入所者との深い関わり」が持て、「個性を大事にした看護ができる」ことで、「施設ケアの喜びを知る」ことができ、「介護職と喜びを分かち合う」までになるのです。特に「最高の看取りを提供できた喜び」は家族からも感謝され、「家族との関係からケアの喜びを感じる」とともに、「病院ではできない経験」で、「特養に来てよかった」「また頑張ろう」と思える原動力になるのだそうです。
まるでドラマのように、特養に来たナースが戸惑いの中から、看護の素晴らしさに目覚め、「施設看護を手探りで見つけて」いき、最後には「特養看護の真髄を見出す」という境涯にまで至るプロセスを、生のインタビューという手法を駆使することで描き切った戸塚さんの分析はお見事でした。しかし、ドラマではそこでハッピーエンドになるのでしょうが、現実はそう甘くはないようです。
まさに「特養看護の真髄を見出す」ことが出来た後も、時にはもう頑張れないと感じるなど、「揺れる心の天秤」が存在したというのです。いかにも人間らしさが伝わってくるようですが、それも生身の人間の生の声を題材にしたからこその成果と言えるでしょう。戸塚さんは以上のような分析から「ジレンマよりもやりがいという肯定的な感情の方が心の中で大きな位置を占めるように自分を調整し、努力していくことが重要」と考察を結びました。
ただ、私としては、やはり看護教育への問題提起で締めて欲しかったという気がしました。確かに「やりながら学ぶ」というのはとても大事なことではありますが、学ぶ前にジレンマのままに挫折して辞めてしまった人もたくさんいたのではなかったでしょうか。見事に乗り越えて、看護の真髄を見出すまでになった人はごくごく少数派だったでしょう。
看護学校、大学の教育の中で、施設看護においても十分に対応できるような教育が行なわれていないことは重大問題です。ただ、新卒者は基礎看護技術のほとんどができないという話を前に書いたこともありましたが、病院看護すらろくに教えられていない現状では、施設看護など望むべくもないのかもしれません。
先日、厚労省の検討会で診療行為の一部ができる日本版ナースプラクティショナーを作る方向が打ち出されました。よりハイレベルなナースの誕生は歓迎すべきだと私は考えています。しかし、それはそれとしても、現実の医療・福祉の現場にキチンと即戦力として対応できるナースを養成していく教育を実現することをないがしろにしたままであるならば、本末転倒と言わざるをえないのではないでしょうか。(以上)